出展者どうしのブース訪問、提案ってどうなの?
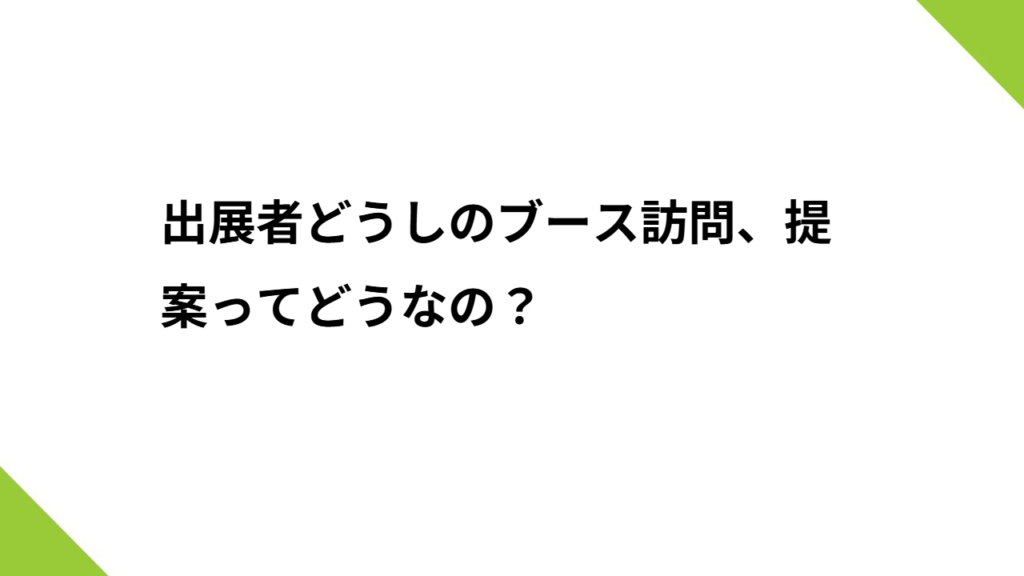
出展者どうしのブース訪問、提案ってどうなの?
~「競合ではなく共創」の視点で考える展示会の裏チャンス~
展示会に出ていると、一度はこんな場面に出会うのではないでしょうか。
「となりのブースの担当者が挨拶に来た」「別の出展者が製品の相談をしてきた」「展示の途中で営業をかけられた」――。
一見、出展者同士は“お客様ではない相手”のように思えますが、実はここに見逃せないビジネスチャンスがあります。
出展者どうしの接点には「裏の展示会」がある
展示会には、公式の来場者(バイヤーや取引希望者)だけでなく、同じく出展している企業担当者が数百人単位で参加しています。
つまり、会場全体が「同業・異業種交流のリアルネットワーク空間」になっているのです。
実際、業界ではこの“出展者間ネットワーキング”がきっかけで共同開発や業務提携に発展することが多くあります。
同じテーマを持つ企業どうしは、課題や顧客層が似ているため、「競合」よりも「協業」の糸口」が見つかりやすいのです。
たとえば、
・製造メーカー × デザイン会社 → 製品開発コラボ
・機械部品メーカー × 商社 → 海外販路の提携
・出展サポート業者 × 出展企業 → 次回イベントの協力関係
このように、展示会の“裏側”では多くのBtoB連携が進んでいます。
ただし、タイミングとマナーが命
とはいえ、出展者同士の訪問や提案には“やってはいけないタイミング”もあります。
最も避けるべきは、来場者対応中のブースに声をかけること。
商談の邪魔をする形になり、印象を悪くしてしまいます。
訪問するなら、朝の開場前・昼休憩・終了直後など、「ブースが落ち着いた時間帯」を狙うのが礼儀です。
また、最初から営業モードに入るのではなく、
「今回どんな目的で出展されていますか?」「私たちも似た分野なんです」など、
共感ベースの会話から入ると相手も受け入れやすくなります。
展示会場では「誰が買い手で、誰が売り手か」が曖昧です。
だからこそ、“フラットな交流”として自然な会話を心がけることが信頼につながります。
提案は“ブース外”でやるのがスマート
展示会中はどの企業も目の前の来場者対応で手一杯。
その場で長く立ち話をしても、記憶に残らないことが多いです。
ですから、ブースでの接触はきっかけづくりと割り切りましょう。
名刺を交換したあと、
「展示会が終わったあとに改めてご相談させてください」
と一言添えるだけで、相手も安心します。
後日、メールで「先日はお会いできてうれしかったです。もし協業の可能性があれば…」と送る。
これが最も自然で成功率の高いアプローチです。
展示会での接点は、“本番の打ち合わせ前の挨拶”と捉えるのが賢いやり方です。
実は主催者も歓迎している
多くの展示会主催者は、出展者どうしの交流を「展示会の成熟」と見ています。
つまり、出展者同士がビジネスを生み出せる場こそが、本来の展示会の価値なのです。
欧州やアジアの展示会では、出展者限定のネットワーキングパーティーや、ブース訪問専用の時間帯を設ける例も増えています。
この潮流を考えると、日本でも「出展者間のつながり」はむしろ推奨される時代になっています。
ただし、営業目的だけではなく、「業界を広げる・情報交換をする」という姿勢で臨むことが大切です。
展示会は“競う場”ではなく“つながる場”
展示会は確かに販促の場ですが、それ以上に業界の共創の場でもあります。
隣のブースに立っている人も、もしかすると将来のビジネスパートナーかもしれません。
一見ライバルに見える企業でも、得意分野が違えば補完関係を築ける。
むしろ、同じ展示会に出ている時点で、すでに「価値観が近い企業」なのです。
ブース訪問や提案は、タイミングとマナーさえ押さえれば、
来場者との商談と同じくらい価値のある「もうひとつの展示効果」になります。
展示会の成功とは、
“どれだけ名刺を集めたか”ではなく、
“どれだけ信頼できるつながりを生み出せたか”で決まります。
まとめ
出展者同士のブース訪問・提案は、やり方次第で強力なネットワーク形成のチャンスになります。
・来場者対応中は避け、落ち着いた時間に訪問する
・営業ではなく「共感・情報交換」から始める
・後日フォローで正式な提案を行う
この3つを意識すれば、展示会の“裏側”に眠るビジネスチャンスを、確実に掴むことができます。
