展示会で名刺交換した人が、購入までにたどる過程を分析してみよう。どのようなオファーを、どのタイミングで行うのかを決めておきましょう。
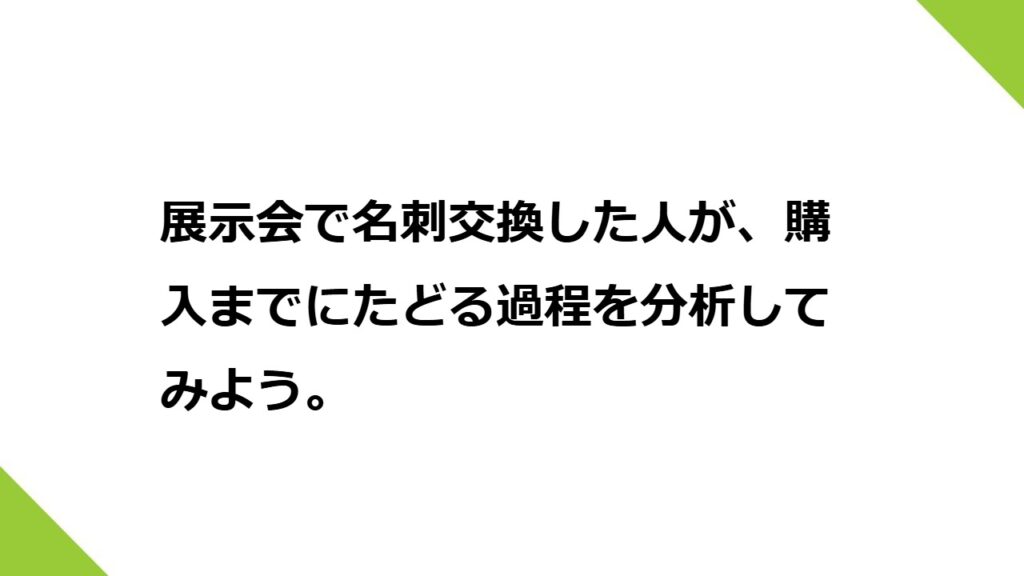
展示会で名刺交換をした人が購入に至るまでの過程を分析し、どのタイミングでどのようなオファーを行うかを決めることは、効果的なリード育成の鍵です。
購入に至るまでの過程は、一般的に「認知→興味→比較→購入検討→購入」といった段階を経ます。
それぞれの段階で適切なオファーを提供することで、リードを次のステップへと進めることができます。
以下に、展示会後のリード育成プロセスと、各段階で行うべきオファーのタイミングについて分析します。
1. 認知段階(展示会後の1週間以内)
展示会で名刺交換した人は、まず自社の製品やサービスについて「認知」してもらうことが最初のステップです。
この段階でリードが最も求めているのは、自社の製品が自分にどのような価値を提供するのかを理解することです。
・オファー例
サンキューメール:展示会での出会いに感謝し、自社の特徴や製品の強みを簡潔に伝える。
すぐに購入を促すのではなく、「もっと知りたい」という気持ちを引き出す。
製品情報の提供:製品やサービスの詳細情報を、例えばホワイトペーパーやカタログのリンクを添えて提供。
・タイミング
展示会後1-3日以内:即座に感謝の意を伝え、さらに関心を引き続けるために情報を提供します。
2. 興味段階(展示会後の1週間から1ヶ月以内)
リードが製品に対してある程度の興味を持ち始める段階です。この段階では、製品の利用シーンやケーススタディを通じて、実際に製品がどのように役立つのかを示すことが重要です。
・オファー例
お試し・デモの提案:興味を持っているリードに対して、製品を実際に体験してもらう「お試し」や「デモンストレーション」を提案します。これにより、製品の効果を自分で体感してもらうことができます。
顧客の声(ケーススタディ):実際の顧客がどのように製品を活用しているかを示す具体的な事例を紹介することで、リードの関心をさらに深めます。
・タイミングは:
展示会後1週間〜1ヶ月:興味を持ち始めたリードには、実際に製品を試せる機会を提供して、購入意欲を高めます。
3. 比較段階(展示会後の1ヶ月〜3ヶ月以内)
リードが他の競合製品と比較し始める段階です。この段階では、製品の独自性や競合との差別化を明確にすることが重要です。
オファー例:
無料トライアルや特別キャンペーンの提供:購入前に製品をお試しいただける期間を提供したり、特別価格や割引を提供することで、リードに購入を後押しします。
FAQや製品仕様に関する詳細情報:リードが疑問点を解消できるよう、よくある質問や製品の詳細なスペックを提供し、購入に対する不安を払拭します。
タイミング:
展示会後1ヶ月〜3ヶ月:比較を行っているリードには、具体的なアクションを促すためのオファー(トライアルや割引など)を提供します。
4. 購入検討段階(展示会後の3ヶ月〜6ヶ月以内)
リードが購入を真剣に検討し始める段階です。この段階では、最後の背中を押すためのオファーを提供することが重要です。
オファー例:
契約や購入の決定を後押しする特典:購入を決断した場合の特典や、限定的なオファーを提案します。例えば、早期購入特典や無料サポートの提供など。
営業担当者との面談の提案:リードが購入に対して確信を持てるよう、営業担当者と直接話をする機会を設けます。
タイミング:
展示会後3ヶ月〜6ヶ月:リードが購入を真剣に検討しているタイミングで、契約を後押しするオファーを提案し、商談をまとめる手助けをします。
5. 購入段階(展示会後の6ヶ月以内)
最終的にリードが購入を決定する段階です。ここでは、購入手続きをスムーズに進めることが重要です。
オファー例:
購入後のサポートやアフターサービスの提案:製品購入後に必要となるサポートやアフターサービスを提案し、顧客の安心感を高めます。
タイミング:
購入決定直後:購入手続きが決まったタイミングで、アフターサポートや関連するサービスを提供し、リピーターや長期的な関係を築く準備をします。
まとめ
展示会で名刺交換をした人が購入に至るまでの過程を分析しておきましょう。
それぞれの段階で、何をすれば効果的なのか、営業部門とあらかじめ定義しておきましょう。これは各社ごとに違うはずです。必勝法を準備しましょう。
各段階で適切なオファーを行い、必勝法に持ち込むことで、展示会で得たリードを実際の購入につなげることができます。ぜひ研究してみてください。
インターネット展示会TVでは、展示会動画の活用をおすすめしています
展示会の出展は、会場だけで終わらせてはいけません。なぜなら、見込み客は会場の中だけに居るわけではないからです。展示会を動画化しオンラインで活用する「展示会動画マーケティング」はこちらのページへどうぞ。

