AIの普及と、Googleなどでの検索の減少・・・これからのマーケティングは「つながり」が鍵。
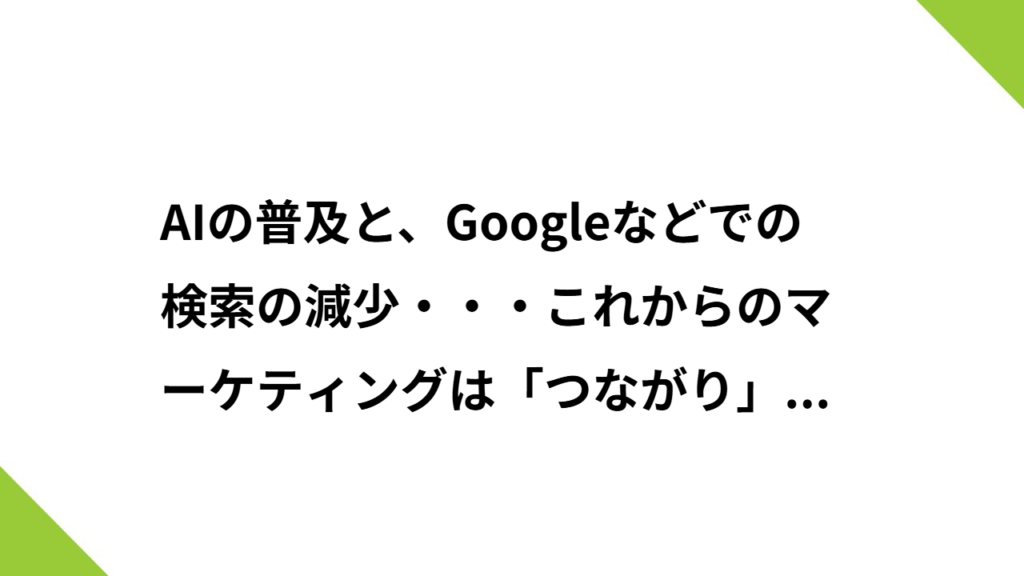
かつてマーケティング施策の中心は、Google検索に最適化された「SEOコンテンツ」や「リスティング広告」でした。ユーザーは疑問があればGoogleに入力し、検索結果に表示されたリンクから情報を取得する。この構造が長らくマーケティングの土台となっていました。
しかし、AIチャットや生成AIの普及により、この構造は今、大きく変わろうとしています。ユーザーは「検索する」よりも「尋ねる」ことを選ぶようになり、AIが瞬時に回答を生成します。結果、Google検索そのものの利用頻度が徐々に減少しているのです。マーケターにとって、これは無視しても良い小さな傾向・・・ではありません。
検索トラフィックが減少すれば、当然ながらSEO施策の効果は下がり、従来の集客施策は頭打ちになります。では、これからの時代においてマーケティングはどの方向へシフトすべきでしょうか?AIに読んでもらうようにチューニングする?新聞広告やタクシー広告など、オフラインに活路を求める?
その答えのひとつが「つながり」にあります。
「つながり」が、ファネルに代わる
従来のマーケティングは「認知→興味→比較→購入」というファネル(漏斗)構造に基づいて設計されてきました。しかし、AIが情報の「比較・評価」を担うようになると、顧客の意思決定プロセスは短縮され、情報の量よりも「信頼できるつながり」からの推薦が重要になってきます。
BtoBでもBtoCでも、今後は「誰から紹介されたのか」「どのような関係性があるのか」が選定基準になります。つまり、コミュニティ・顧客との関係性・リアルな接点こそが、新たなマーケティング資産となるのです。
「つながり」の時代に、展示会は評価されるべきリアルチャネルである
AIの普及により、検索による情報収集が自動化・省略される今、ユーザーの意思決定は「信頼」や「関係性」といった“人とのつながり”に強く依存するようになってきています。つまり、これまでのように「検索上位に出るから選ばれる」のではなく、「信頼している人が推しているから選ばれる」という構造が一般化してきたのです。
このような環境において、展示会は注目すべきマーケティング施策となります。なぜなら展示会は、リアルで人と出会い、会話し、空気感ごとブランド体験を提供できる場だからです。デジタルでは難しい「人の温度」「対面の説得力」「偶然の出会い」など、つながりを深めるうえで欠かせない要素がここには詰まっています。
「つながり」を軸にした展示会の運用とは?
展示会において重視すべきは、従来の「名刺獲得数」や「リードの量」だけではありません。むしろ、誰とどのような関係を築けたか、ファン化の種をまけたかが問われます。そのための具体的な運用方針はどのようなものがあるのでしょうか。
1. “刺さる”メッセージを事前に設計する
単なる製品の説明や機能訴求ではなく、「自社がどんな世界観を目指し、どんな顧客と伴走したいのか」というメッセージをブース全体で表現します。それが来場者との共感ポイントになります。
2. 接客は「売る」ではなく「対話する」
展示会場での接客は「製品説明」より「顧客の価値観を理解する場」にすべきです。来場者の背景や課題を聞き取り、「この人と長く付き合えるか」を見極めるコミュニケーションを重視しましょう。
3. 名刺の“質”を記録する仕組みを
名刺交換時に、その場で気づいたポイント(関心・温度感・話題)をCRMや記録シートにメモする運用を徹底しましょう。「誰とどう話したか」は、後のフォローアップの質を大きく左右します。
4. 展示会後の“つながり強化”こそ本番
展示会で接点を持った方には、イベント後のセミナー招待、個別訪問、SNS上での再接点などを活用し、「ただの名刺交換」から「関係性のある接点」へと育てていくことが重要です。
展示会を「つながりの起点」に
AIによって“情報の壁”が低くなればなるほど、企業やブランドが差別化できるのは「どれだけ顧客とつながれているか」という関係性の深さです。AI時代のマーケティングでは、「情報を届ける」より「関係を築く」ことが、これまで以上に成果を左右するでしょう。
AIがもたらす合理化の波に対し、人間的なつながりの価値はむしろ高まっています。展示会はその「リアルな起点」として、デジタル施策では得られない濃い接点を生み出す貴重な場です。ただし、ただ立ち並んで説明するだけの“古い展示会運用”では効果は出ません。
これからの展示会は、「未来のファンとの出会いの場」として、ストーリー性・対話・つながりを重視した運用が必要です。展示会を、単なるリード獲得施策から、「ブランド体験と人の信頼を育てる活動」へと昇華させていきましょう。
Googleトラフィックが減ったからと焦るのではなく、それをチャンスと捉え、「つながり」を軸にした新しいマーケティングに踏み出すことが、今まさに求められています。
