マーケティングオートメーションを使っているなら「展示会動画」を活用するべき理由
- Know-how
- 展示会ウオッチ
-
7月 07
- Share post
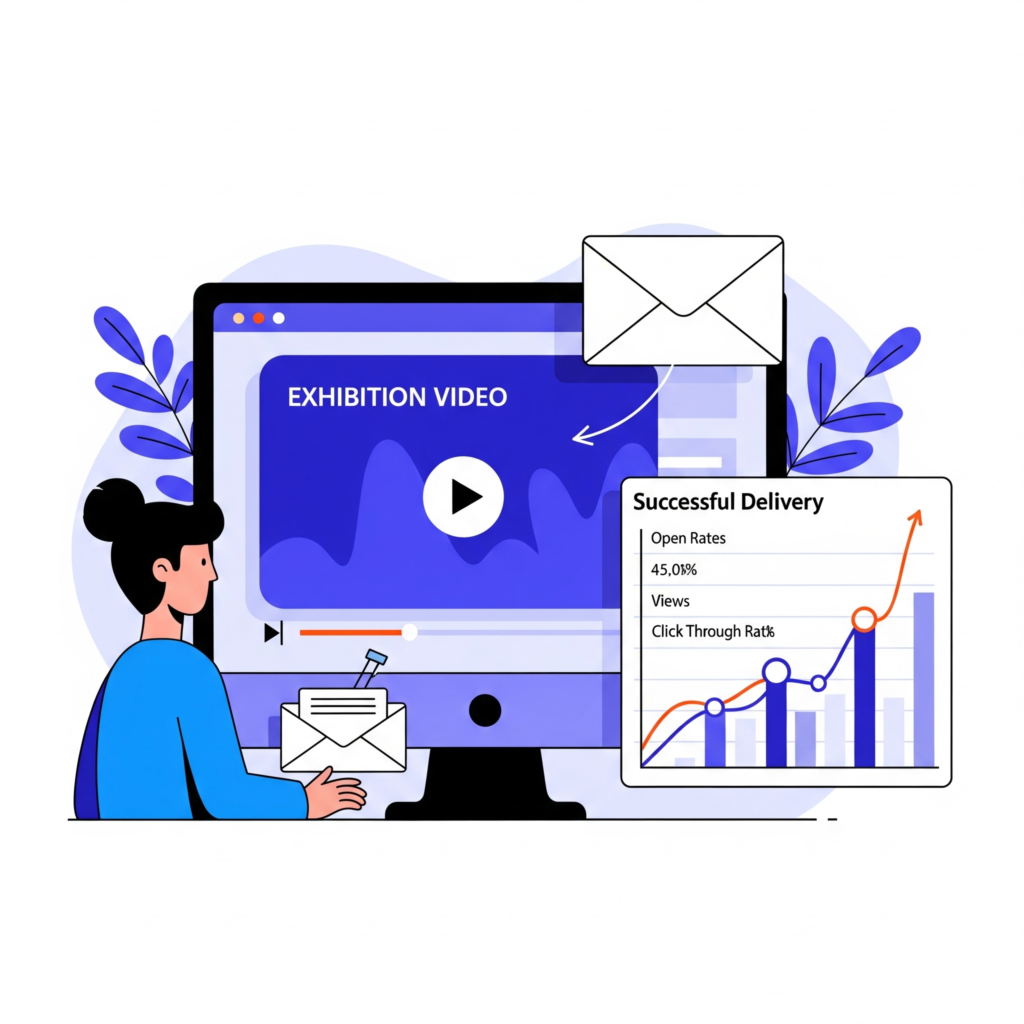
展示会動画 × マーケティングオートメーション
― 印象に残る、成果につながるフォローアップの武器 ―
展示会は従来、製品やサービスをリアルの場で紹介し、名刺交換や商談を通じて新たなビジネスチャンスを創出する場として活用されてきました。
しかし近年では、それだけにとどまらず、デジタルマーケティングに活用可能な”一次情報の宝庫”としても注目されています。
特に、展示会で撮影された動画は、その臨場感・リアル感を保ったまま再利用ができるという点で、マーケティングオートメーション(MA)との相性が非常に高いコンテンツなのです。
なぜ「展示会動画」なのか?
展示会は、製品やサービスの魅力をその場で伝えることができる数少ないリアルチャネルです。
来場者は製品を見て、説明を聞き、実演やデモンストレーションを通じて実体験を通して体感し、納得感を得ます。
その一方で、展示会の情報はその期間に会場に行かないと得ることができない、そして、時間と共に忘れられてしまう、という課題があります。
しかし、展示会で撮影した動画には、その瞬間の熱量や空気感、担当者の熱意、来場者のリアクションといった、“テキストでは表現しきれない価値”が詰まっています。
このコンテンツをデジタル化して保存・配信することで、来場できなかった顧客にもアプローチでき、記憶が薄れつつある来場者にも再びアプローチすることが可能になります。
特にマーケティングオートメーションと組み合わせることで、動画の視聴履歴や視聴時間、視聴完了率といった行動データを取得でき、より精度の高いナーチャリングやスコアリングにつなげることができます。
展示会では「印象が埋もれる」のが当たり前
展示会は、数十、場合によっては数百社の企業が集まり、来場者も短い時間で多くのブースを回ることになります。そのため、「面白かった」「印象に残った」と思ったブースであっても、数日後には名前すら思い出せないというケースが非常に多いのです。
なぜ印象が薄れるのか?
-
- 情報が多すぎる:1日で5〜10社、またはそれ以上の情報に触れると、内容が混ざって記憶に残らない。
-
- ブースの類似性:同じ業界・カテゴリの企業が似た展示をしていると、印象が曖昧になる。
-
- 一律なフォローアップ:展示会後に送られるのが、「なにかありましたらご連絡ください」などの定型文メールだけでは、印象が蘇らない。
これらの課題を解決するのが「展示会動画」です。展示会で撮影した動画は、映像・音声・ストーリーという三位一体の要素によって、来場者の記憶に直接アクセスし、再び関心を喚起させる力があります。
MA × 展示会動画の活用シーン
1. 来場者へのフォローアップ
展示会後のフォローアップは、営業活動において極めて重要です。来場者に対して、「ご来場ありがとうございました」というメッセージと共に、ブースでの紹介動画を添えて送信すれば、来場時の体験をもう一度想起させることができます。
また、「パンフレットだけもらう」来場者には、より詳しく製品の特徴やメリットを伝える良いチャンスになります。
動画の内容は汎用的なものだけでなく、個別製品やソリューションに特化した内容に分けることで、パーソナライズされたフォローも可能になります。
2. 来場していない顧客への接触
展示会に来られなかった既存顧客や、MA上でスコアが高まってきた見込み顧客に対しても、「展示会で紹介した新製品の動画です」とアプローチすることで、新たな関心を引き出すことができます。
展示会のネーミングバリューを利用し、クリックしてもらうという動機づけも可能です。
また、動画の再生回数や再生時間などの行動履歴をトラッキングし、興味度に応じたアクション(例:資料送付、営業の架電)を自動化できる点がMAの強みです。
3. 視聴データによるスコアリング・セグメント分け
-
- 最後まで視聴した → 高関心 → 優先的な営業アプローチ
-
- 中盤で離脱した → 興味はあるが刺さっていない → メッセージの見直し
-
- クリックしなかった → 関心低 → 保留 or セグメント変更
こうしたデータをもとに、行動に応じたリードの分類・対応優先順位の最適化が可能になります。
成果につながる展示会動画の4つの工夫
1. 短く・わかりやすく(1〜2分)
展示会後の動画は「見てもらえるかどうか」がすべてです。忙しいビジネスパーソンにとって、長い動画は敬遠されがち。1〜2分以内に収めた簡潔な動画こそが、視聴・理解・行動につながります。
この時間内で「どんな課題に対して」「どんな製品・サービスが」「どのように解決するのか」を、シンプルに伝える構成が重要なのです。
2. 「課題→解決策→成果」のストーリー設計
動画の構成として効果的なのは、下記の3ステップ。
-
- 課題提示:例えば、「人手不足で作業が滞っていませんか?」
-
- 解決策の提示:「この自動搬送ロボットなら、30%の作業時間短縮が可能です」
-
- 解決理由の明示:視覚的にわかるように→「このように、ロボットに作業を分担させることによって〇〇が可能となっています」
このように、ストーリー性を持たせることで、視聴者に“自分ごと”として捉えてもらいやすくなります。
3. 字幕・テロップで視聴環境に配慮
オフィスや移動中など、音を出せない環境で視聴されるケースは増えています。したがって、字幕とテロップは情報伝達のための必須要素です。
さらに、キーワードや数値を強調することで、視覚的な記憶定着にも効果を発揮します。
4. ロゴ・展示会風景で信頼感を演出
企業ロゴや実際の展示会ブース、担当者の受け答えといったシーンは、言葉以上に「ちゃんと存在する企業だ」という実在性と安心感」を与える視覚的証拠となります。
これは、見込み顧客にとって心理的ハードルを下げ、問い合わせ・商談につながりやすくなる重要なポイントです。
動画は”一度きり”ではない
展示会動画は、展示会直後だけのコンテンツではありません。例えば:
-
- 製品説明ページで利用
-
- 一部を切り出してSNS用に再編集
-
- 資料請求フォームのページで活用
-
- 営業メールの署名欄に設置
といったように、多用途に展開できる”資産型のコンテンツ”なのです。MA以外にも活用してくださいね。
展示会動画は「感情を動かすMAコンテンツ」
マーケティングオートメーションにおいて、展示会動画は「人の心に残る」コンテンツです。
テキストやPDF資料だけでは伝えきれない熱意・空気感・現場のリアリティを映像で届けることで、記憶に残り、アクションを生み出します。
振り返って自分ごととして考えてみても、やっぱり動画のほうが興味を引いたり、クリックしたくなりますものね。
MAと組み合わせることで、動画をトリガーにした精度の高いフォローアップやスコアリングが可能になり、商談化率や受注率の向上にもつながります。
展示会を「その場限りのイベント」で終わらせず、デジタルマーケティングの起点として活用するために、展示会動画の活用をぜひご検討ください。
インターネット展示会TVでは、展示会動画の活用をおすすめしています
展示会の出展は、会場だけで終わらせてはいけません。なぜなら、見込み客は会場の中だけに居るわけではないからです。展示会を動画化しオンラインで活用する「展示会動画マーケティング」はこちらのページへどうぞ。

